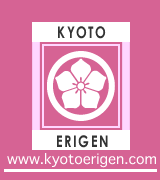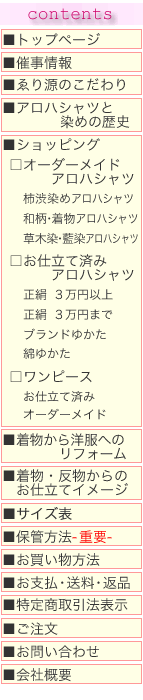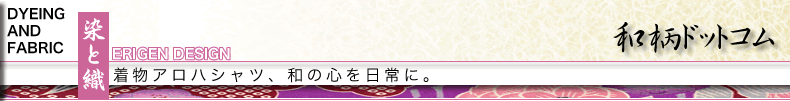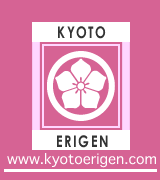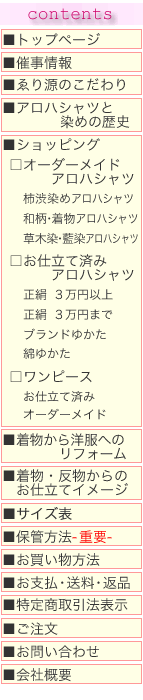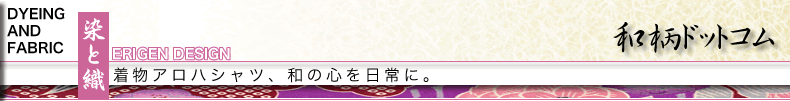藍染めの歴史は古く、エジプトのテーベ遺跡で発掘された紀元前2000年頃のミイラに、藍で染めた麻布が巻かれていました。その後、藍染めはインド・中国へと広がっていきます。
インドでは、インド原産の青色染材としてインジカンと呼ぶようになり、これが藍の代名詞「インディゴ」となりました。
中国では、紀元前一世紀頃から筍子の「青は之を藍に取りて、藍よりも青し」との名言もあります。また、当初藍は薬用にも用いられ、漢方薬としても使われていました。
アメリカでは藍の染色布は蛇などの爬虫類が嫌うとされていて、200年前からアメリカのカウボーイたちが藍の葉をジーンズの染色に用いていました。
それでは、藍はいつごろ日本に入ってきたのか?現存する最古の藍染品は、奈良の法隆寺(607年)、および正倉院(756年)に藍の組織として残っていることから、おそらく遣隋使(607〜614年)か遣唐使(630〜894年)が持ち帰ったものだとされています。
その後、平安時代・室町時代と様々な藍染めが行われ、江戸時代には綿の栽培が普及し、藍が木綿に良く染め着くことから、一気に庶民の色として発達しました。また、毒虫が藍を嫌うとされていたため、礼服の八割が藍染め品となりました。
しかし、1900年代に入り、安価なインド藍(インディゴ)や人造藍の輸入により、日本の天然藍は衰退の一途をたどりましたが、天然藍のもつ「風合い」や「深みのある色」は人造藍で出すのは難しく、伝統的な本藍染めの要望は依然として根強く残っており、多くの紺屋たちによって引き継がれています。
TOPページへ